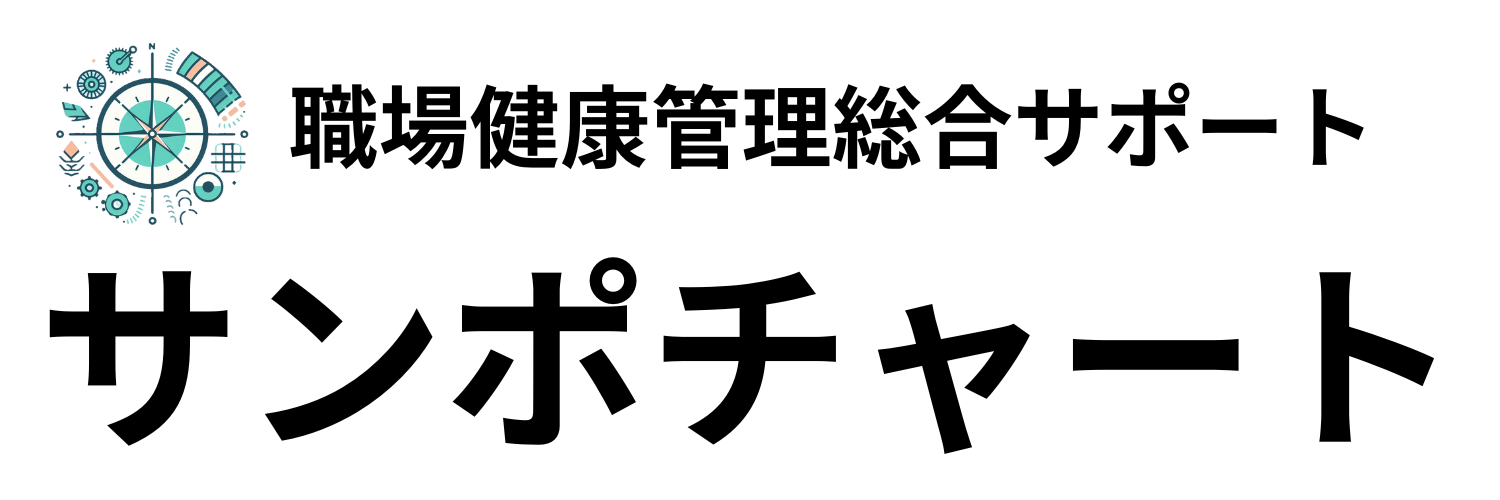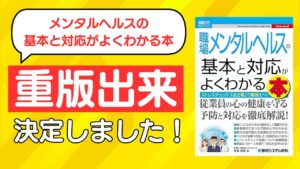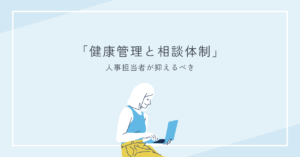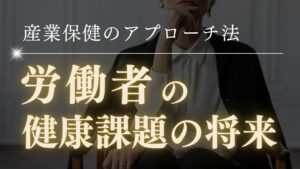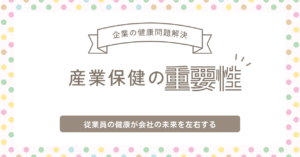「今年も健康診断の季節が来てしまった…」
「今年こそスムーズに処理したい」
このように感じる人事担当者は多いのではないでしょうか。
実施時期の決定から従業員への周知、結果の保管や有所見者のフォローなど、やるべきことは山積みです。
企業の健康診断は法令で義務づけられているため、1つでも漏れがあると、企業としてのリスクにもつながります。
本記事では、人事担当が行う健康診断の処理を6つのステップに整理しつつ、効率化するための具体策も紹介しています。
健康診断の処理を「安心して運用できる仕組み」へと変えるために、ぜひ最後までご覧ください。
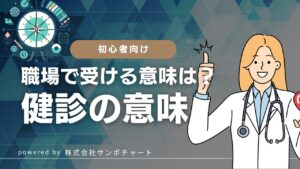
人事担当が健康診断で処理すること6つ
人事担当が健康診断で処理することは多岐に渡ります。以下の内容について、それぞれ見ていきましょう。
- 健康診断の計画と準備をする
- 健康診断を実施する
- 健康診断の結果を従業員へ通知する
- 有所見者をフォローする
- 健康診断の結果を保管する
- 労働基準監督署に結果を提出する(従業員50人以上)
健康診断の計画と準備をする
健康診断を円滑に実施するためには、早期の計画と準備が必要です。以下の内容について、それぞれ解説します。
- 健康診断の実施時期を決める
- 健診機関を選定する
- 対象者をリストアップする
- 従業員に案内を通知する
健康診断の実施時期を決める
健康診断は「年1回以上の実施」が法律で義務づけられていますが、時期の指定はありません。そのため、業務の繁忙期や、夏休みや冬休みなどの長期休暇を避けて行うのが一般的です。
健診機関の予約状況や社内会議のスケジュールも考慮し、3ヶ月〜6ヶ月前から準備を始めるとよいでしょう。
過去の実施時期を参考にしつつ、産業医や上司と相談し、全社的に受診しやすい時期を選びます。早めに決定すると、健診機関の日程確保もスムーズに進むでしょう。
健診機関を選定する
健診機関を選定する際は、以下の内容をチェックします。
- 企業向けの健診に対応しているか
- 労働安全衛生法に基づく検査項目が含まれているか
- 予約の取りやすさや日程調整は問題ないか
- (外部で実施する場合)健診会場が従業員の負担にならない場所にあるか
- (社内で実施する場合)出張健診に対応しているか
- 結果はどのような方法で届くのか(紙またはデータ)
- 費用と請求方法(1人あたりの費用や請求書が届くタイミング)
これらをチェックしたうえで健診機関を選定すると、健康診断の処理を円滑に行えるでしょう。
対象者をリストアップする
健康診断の対象者は「常時使用する従業員(正社員、契約社員、パート、アルバイト)」です。「常時使用する労働者」の定義は次のとおりです。
- 雇用期間が1年以上の労働者(特定業務の場合は6ヶ月以上)
・期間の定めのない労働者
・契約期間が1年以上の労働者
・契約更新により1年以上雇用される予定の労働者
・すでに1年以上雇用されている労働者 - 週の所定労働時間が正社員の概ね3/4以上(週30時間が目安)
人事データベースから最新の在籍者情報を抽出し、新入社員や中途採用者、休職者の取り扱いを確認したうえでリストを作成します。
人事異動が反映されているかをチェックし、必要に応じて各部署の上司にも確認しながら、正確な名簿を作成しましょう。
従業員に案内を通知する
健康診断の実施概要が決まったら、従業員に案内を通知します。健康診断の案内文には、日程や会場、持ち物、絶食などの注意事項を分かりやすく記載します。
また、メールや掲示板、チャットツールなど、複数の手段を活用して、従業員へ確実に周知できるよう配慮しましょう。
また、受診忘れを防ぐためにリマインドメールを送信したり、上司からの声かけを依頼するなど、フォロー体制もあわせて整備しておくと安心です。
健康診断を実施する
健康診断は社内で実施する場合と、社外の医療機関で行う場合の2種類があり、いずれも期間内に受診するよう従業員に周知することが大切です。
以下の内容についてそれぞれ説明します。
- 会場の設営や受付を行う(社内で実施する場合)
- 受診忘れを防ぐためにフォローする
会場の設営や受付を行う(社内で実施する場合)
社内で健康診断を実施する場合は、健診機関と打ち合わせを行い、必要なスペースや備品(机、椅子、パーテーション、電源など)を用意しましょう。
会場内の導線設計や受付の配置、受診順序の決定もスムーズな運営に必要です。
当日は人事担当や総務担当、健康保険組合のメンバーが受付を担当する場合が多いため、実施の流れを事前に把握すると円滑に進められるでしょう。
受診忘れを防ぐためにフォローする
健康診断の案内を通知しても「仕事で忙しかった」「面倒なので健康診断に行かなかった」などの理由で受診しない従業員もいます。
そのため、受診前にリマインドメールを送ったり、所属部署の上司から声かけをしてもらったりなどのフォローが必要です。
それでも受診しない場合は、法令違反に該当する可能性があることを伝え、必ず受けるよう伝えましょう。
就業規則に「健康診断の受診義務」を明記しておくと、未受診者への対応がしやすくなります。
健康診断の結果を従業員へ通知する
健康診断の結果が届いたら、個人情報保護を徹底したうえで、速やかに本人へ届けましょう。紙で配布する場合は、密封された状態で手渡しまたは郵送します。
近年では、Webポータルで結果を閲覧できるようになりました。健診機関が提供する専用サイトに各自でログインすると、診断結果が確認できます。
「PDF形式でのダウンロードが可能」「スマホでも見られる」などのサービスもあり、利便性が高いのが特長です。
Webポータルが利用できると紙の配布が不要になるため、人事担当者の業務負担が軽減できるうえ、書類の紛失も防げるでしょう。
有所見者をフォローする
健康診断で「所見あり」と判定された従業員には、結果の通知とともに医療機関の受診を促す案内を行いましょう。
また、必要に応じて産業医面談を実施し、就業上の配慮や生活習慣の見直しなどについてアドバイスを提供します。
対応した内容は記録として、健康診断の結果と一緒に保管しましょう。また、再検査の実施確認や健康状態の経過観察など、継続的なフォローも必要です。
従業員のプライバシーを尊重しながら、健康リスクの早期発見と対策を徹底しましょう。
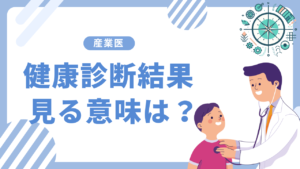
健康診断の結果を保管する
労働安全衛生法に基づき、会社は健康診断の結果を5年間保存する義務があります。保管方法は紙と電子のいずれでも問題ありません。
個人情報を含むため、アクセス制限や施錠管理、パスワードの保護などを厳格に管理して、紛失や漏えいを防ぎましょう。
また、監査や労働基準監督署の調査に備えて、必要書類は常に整理された状態で保管することが重要です。
労働基準監督署に結果を提出する(従業員50人以上)
常時50人以上の労働者を使用する事業所は、健康診断の後に「定期健康診断結果報告書」を作成し、所轄の労働基準監督署へ提出する義務があります。
書類の提出を怠ると、法令違反として指導対象になることもあるため、注意が必要です。
この「50名以上」は正社員だけでなく、契約社員やパート、アルバイトも含む人数で「常時使用しているか」が判断基準です。
また、同一事業所(本社や支店、営業所など)ごとの人数でカウントします。
提出する際は、以下いずれかの方法を選択します。
- 管轄の労働基準監督署へ直接持参
(控えが必要な場合は2部持参し、1部に受付印を押してもらう) - 管轄の労働基準監督署へ郵送
(控えが必要な場合は、切手付きの返信用封筒と控えを同封する) - 電子申請(e-Gov)
健康診断の結果が揃ったら、定期健康診断結果報告書を作成し、速やかに提出しましょう。
健康診断業務の効率化3選
健康診断の業務は実施計画から従業員への案内、フォローや結果の管理まで多岐に渡るため、人事担当者の負担が大きくなりがちです。
そのため、業務を効率化すると担当者の負担軽減だけでなく、全体最適も図れるでしょう。効率化する方法を3つ、それぞれ紹介します。
- 健康診断の管理システムを導入する
- 健康診断の結果をデータにする
- 代行サービスを利用する
健康診断の管理システムを導入する
健康診断業務の効率化を図るうえで、管理システムの導入は非常に効果的です。
対象者の抽出や受診状況、案内文の自動送信、結果の保管や集計までを一元管理できるため、作業の抜け漏れやヒューマンエラーを大幅に削減できます。
さらに、労働基準監督署へ提出する報告書の作成もスムーズに行えるため、人事担当者の業務負担が減らせるうえ、法令遵守の面でも大きな効果を発揮します。
健康診断の結果をデータにする
健康診断の結果をデータにすると、健康管理が効率的に行えます。従業員ごとの健康状態を一覧で把握できるため、体調の変化やリスクの兆候に対応しやすくなります。
また、部門ごとの健康傾向を分析すると、職場環境や働き方の改善にも活かせるでしょう。
紙の管理と比べて検索や集計が容易なため、産業医との連携や健康施策の立案にも役立ちます。健康経営を推進するうえで、データ活用は大きな強みになります。
代行サービスを利用する
健康診断業務を効率化するうえで、外部の代行サービスを活用することは非常に有効な手段です。
受診対象者の管理や案内の通知、健診機関との調整、結果の集計や保管までを一括して任せられるため、人事担当の業務負担を大幅に軽減できます。
さらに、法令に準拠した対応や最新の管理ノウハウに基づくサポートが受けられるのも大きな魅力です。
作業ミスのリスクも減るため、限られた人員体制でも健康診断の業務をスムーズに進められるでしょう。
まとめ
人事担当が健康診断で処理すべき内容と、業務を効率化するための具体的な方法について解説しました。
健康診断は法令対応だけでなく、従業員の健康を守るための重要な役割も担っています。人事担当にとって負担が大きい業務だからこそ、計画的な準備と業務の効率化が欠かせません。
本記事で紹介した6つのステップを押さえつつ、効率化の方法を実践すると、健康診断の処理をスムーズに進められます。無理なく安心して運用できる体制を整えていきましょう。