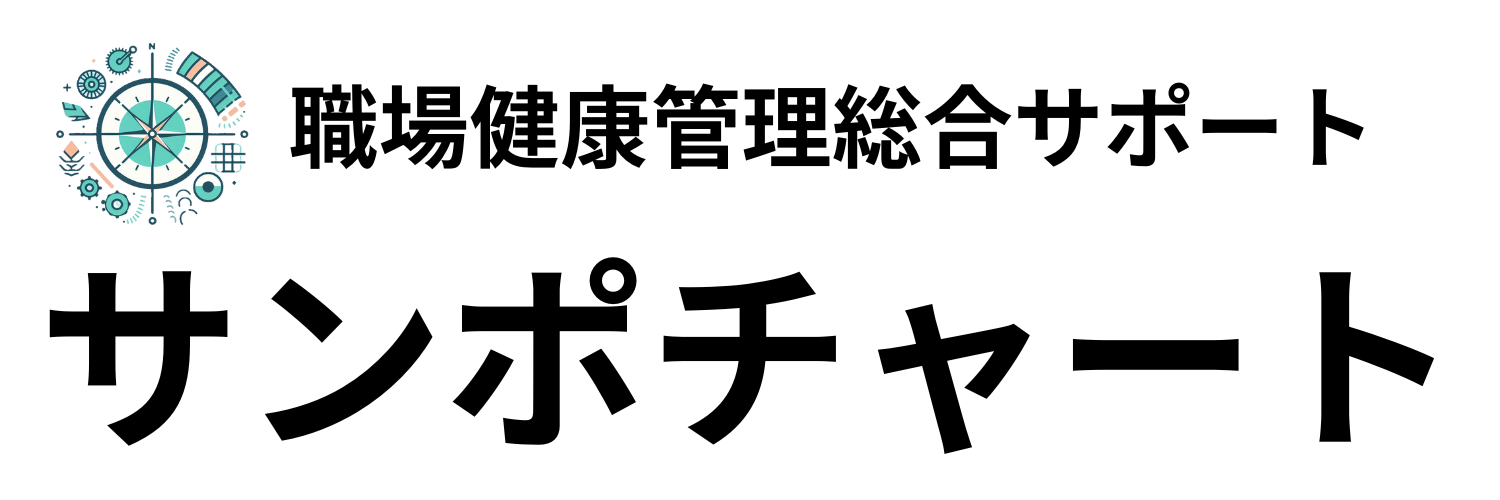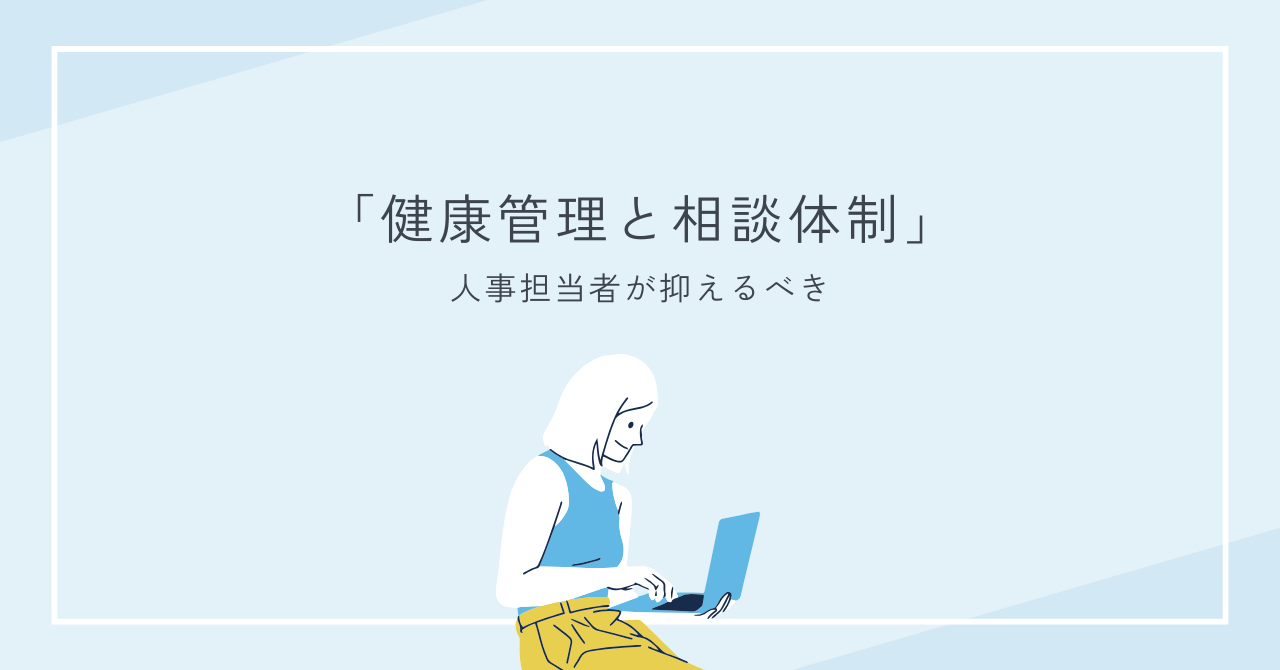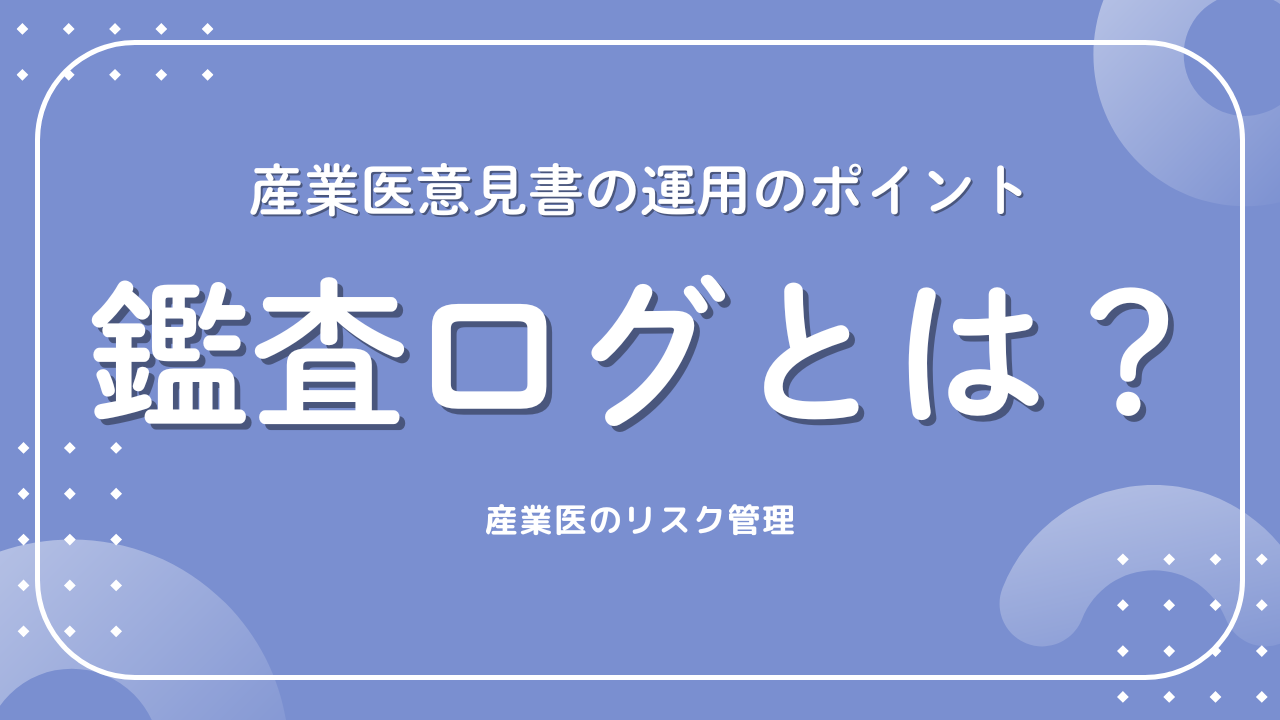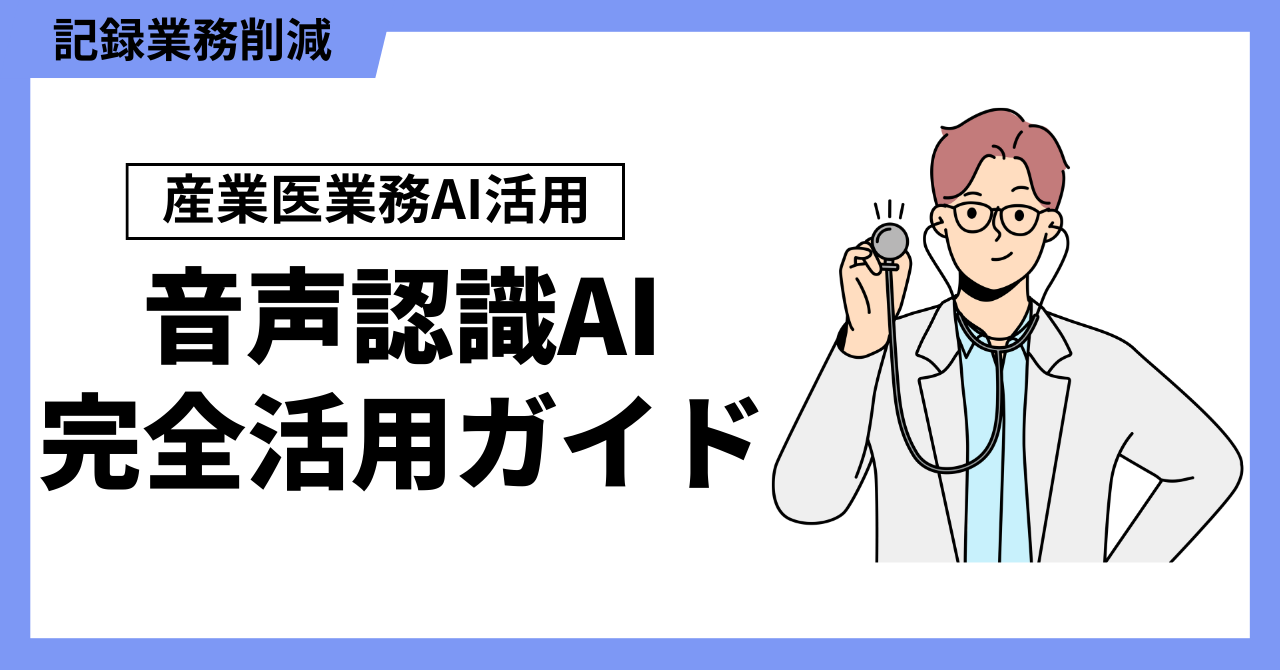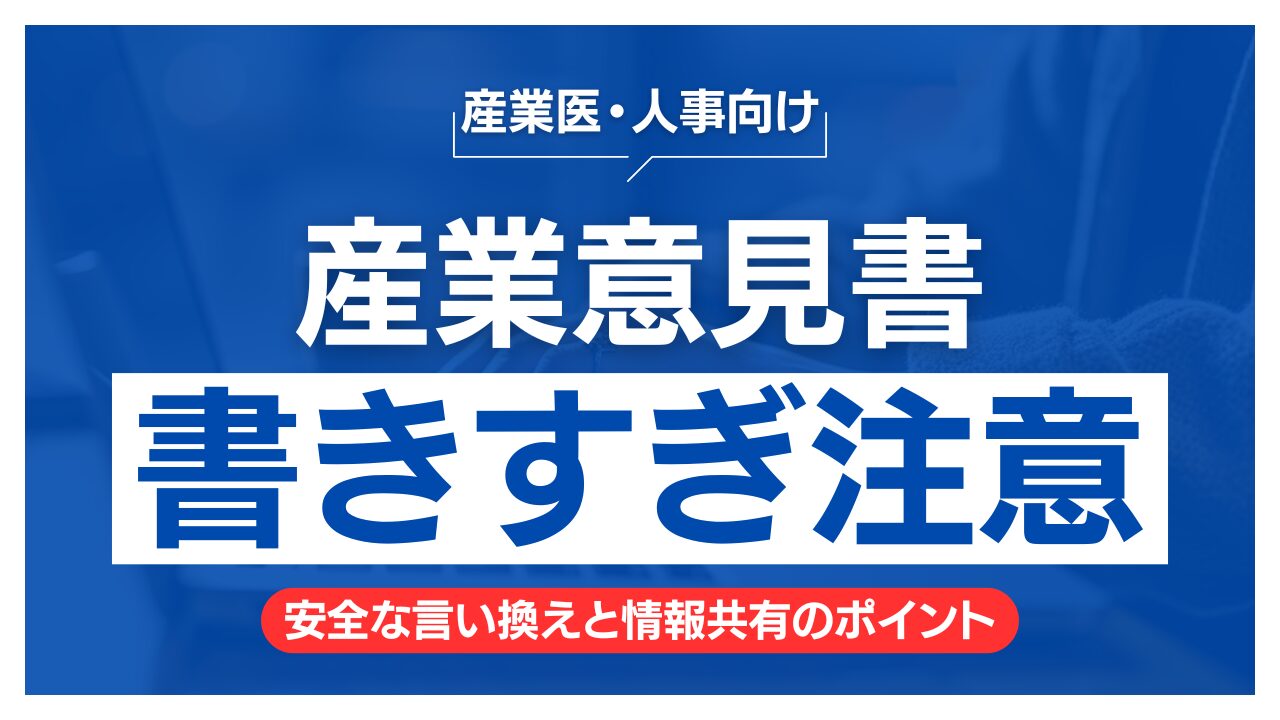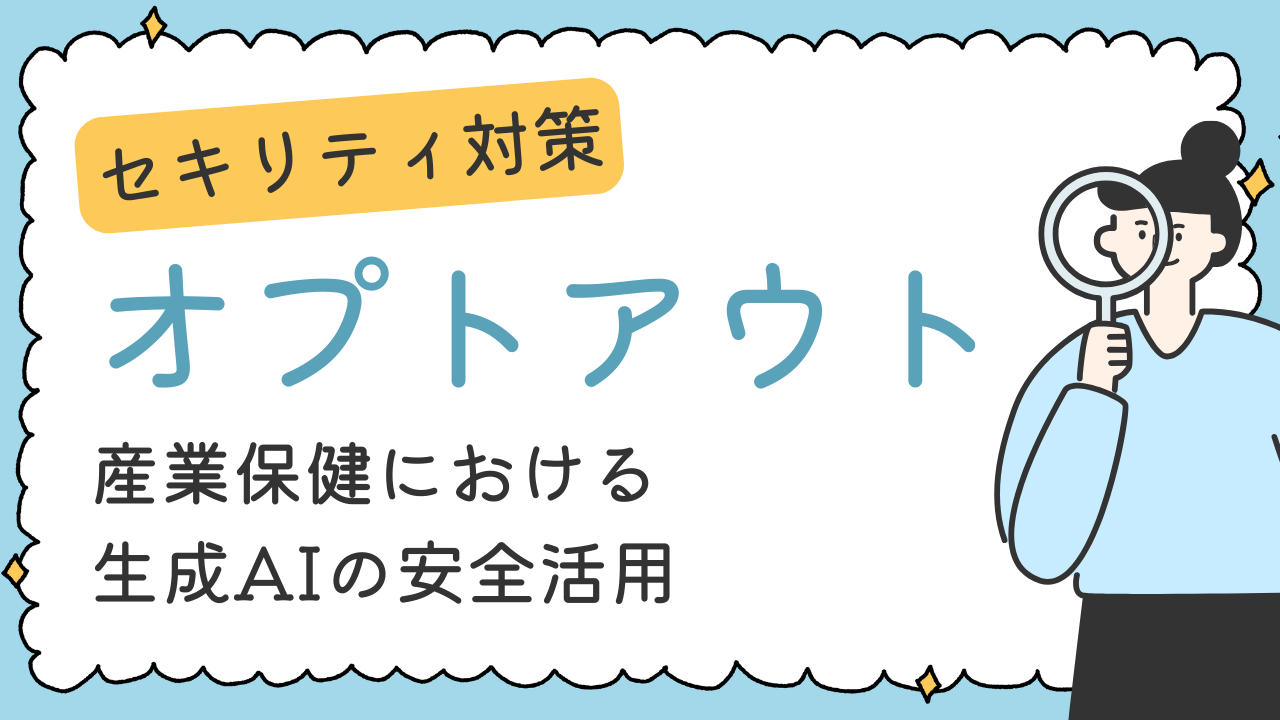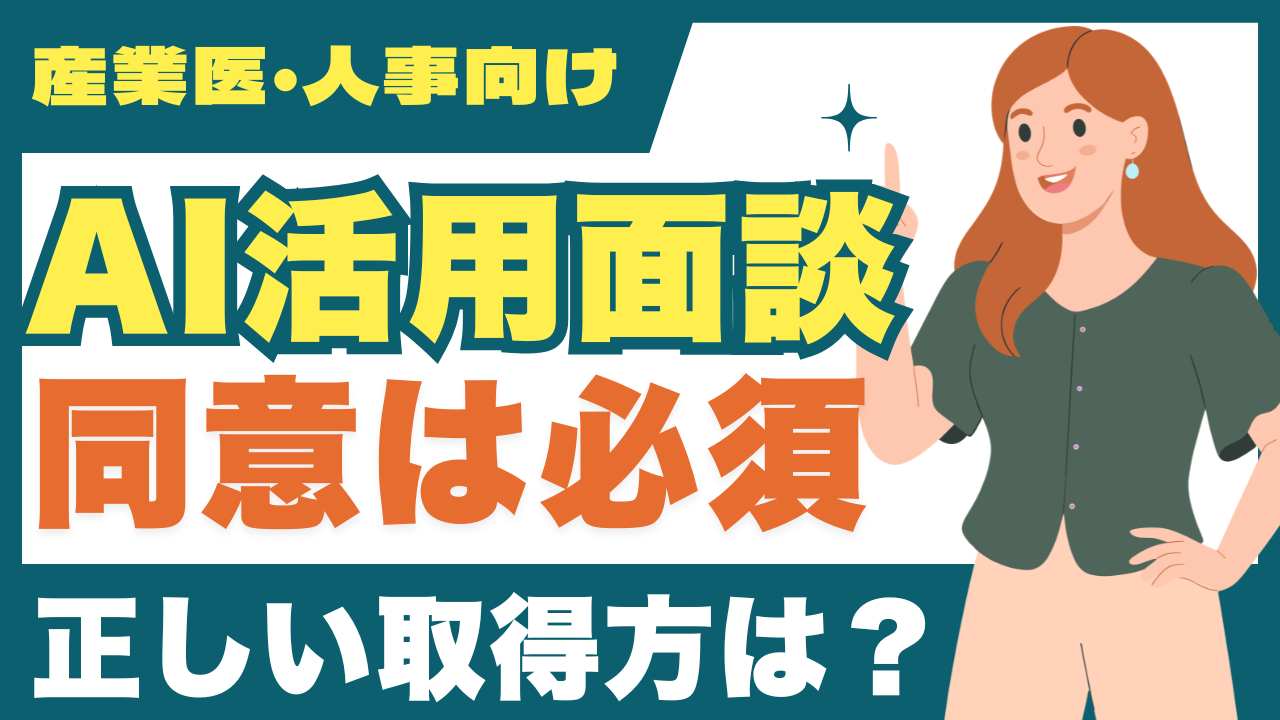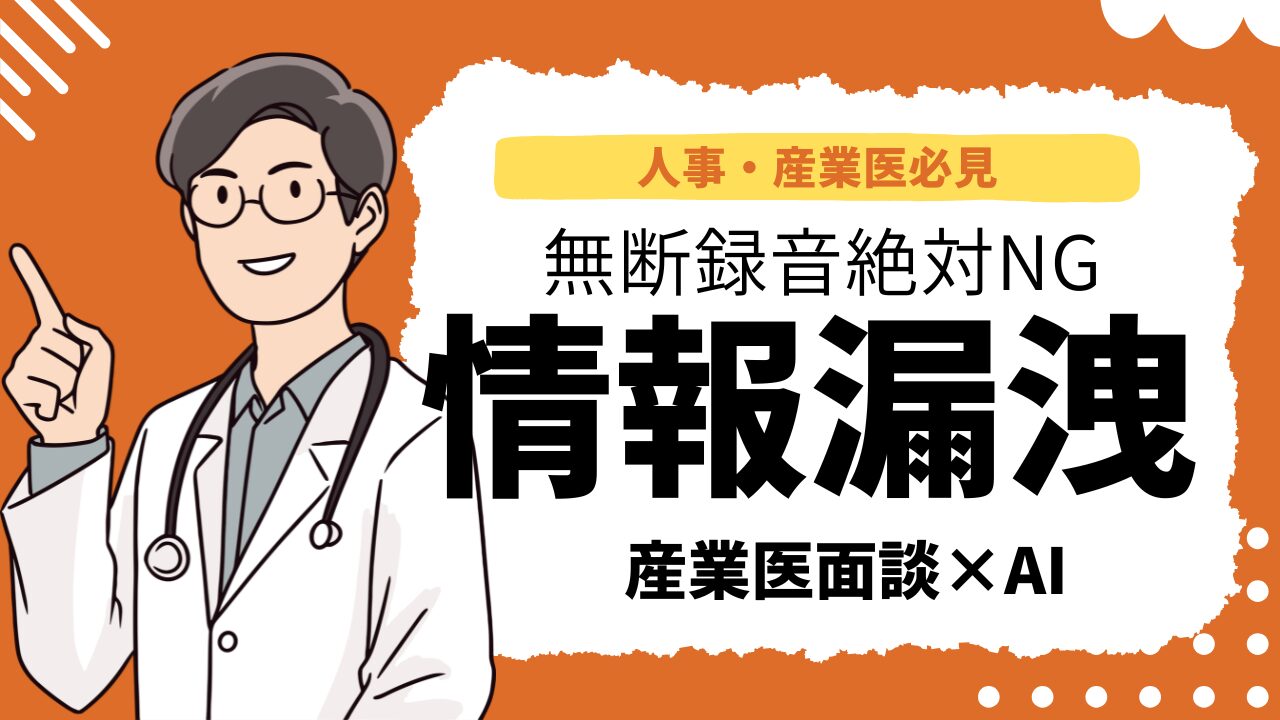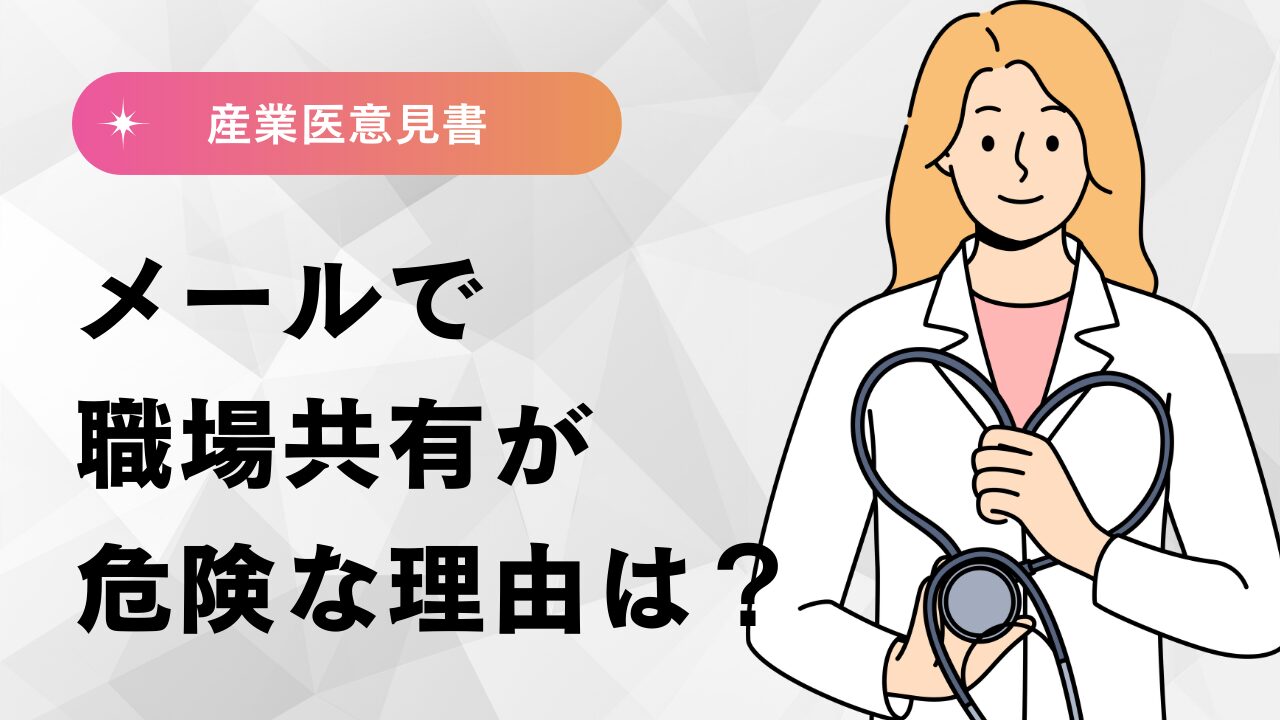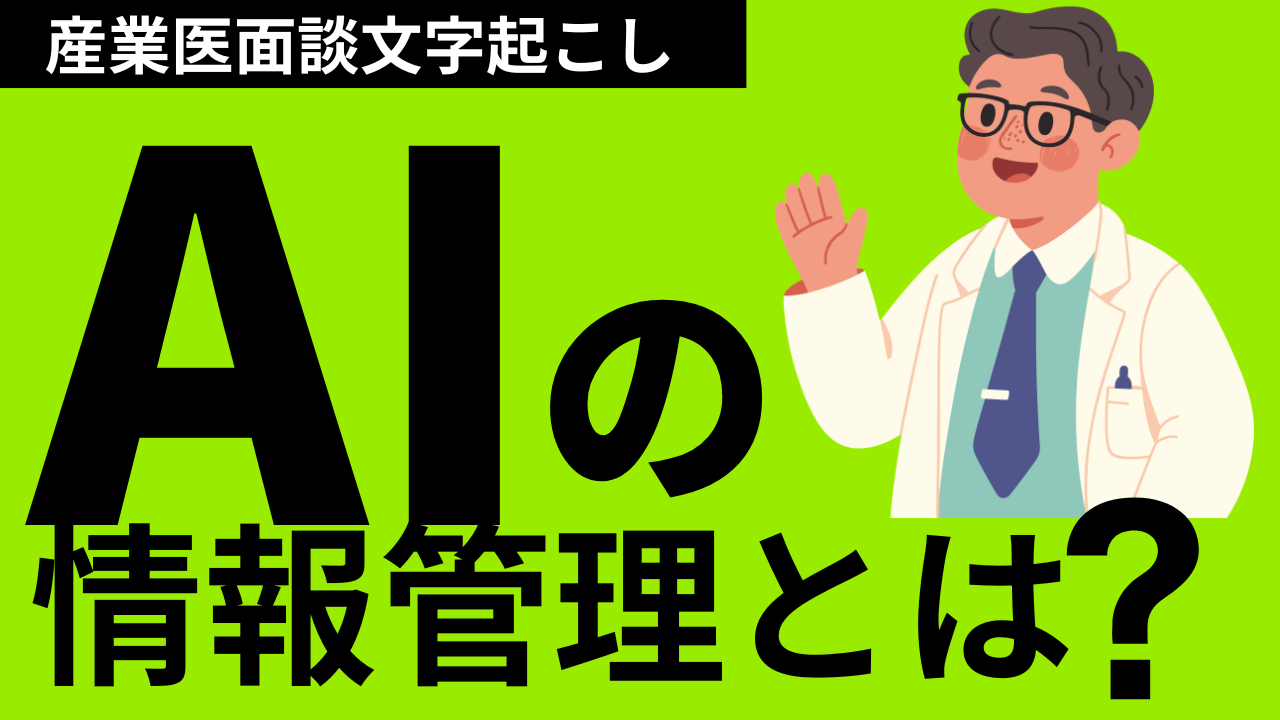「メンタル不調者が増えているけれど、どのようにケアすればいいのか分からない」
「従業員が利用しやすい相談体制の構築方法を知りたい」
と考えていませんか。
従業員の健康管理は、組織の生産性や離職率に直結する重要なテーマです。また、メンタルケアを含む健康管理は繊細な問題のため、対応を誤ると問題が大きくなる可能性があります。
本記事では、人事担当者が押さえるべき健康管理の基本と、従業員が安心して相談できる体制の構築方法について実践的なノウハウをお伝えします。ぜひ最後までご覧ください。
人事担当者が押さえるべき従業員の健康管理
従業員の健康管理は職場全体の生産性を高め、離職率を下げるための重要な施策です。従業員が毎日生き生きと働ける環境を整えると、モチベーションやパフォーマンスの向上にもつながるでしょう。
本章では人事担当者が押さえるべき従業員の健康管理について、社内と社外で対応できる領域に分けて解説します。
- 社内で対応できる領域
- 社外連携がおすすめの領域
社内で対応できる領域
人事担当者が社内で対応できるのは、予防型の健康管理が主な領域です。従業員が健康で快適に働ける環境を整えるため、以下の内容に注力しましょう。それぞれの具体的な方法について解説します。
- 長時間労働の防止
- 快適な職場環境づくり
- 社内・社外相談窓口の整備
- 社内担当者の育成とスキルアップ
- 健康診断の実施とフォロー
- ストレスチェックの実施と結果の活用
長時間労働の防止
労働時間の管理は、従業員の健康を守りながら業務効率を向上させる上で欠かせない取り組みです。しかし、多くの企業では特定の部署で残業が常態化するケースが見られます。これを解決するためには、以下の対策を講じることが重要です。
- 勤怠管理ツールの導入
- 労働時間のデータ分析
- トップダウンからの働きかけ
上記の対応を行なっても労働時間の削減が難しい場合は、要員計画に問題があるかもしれません。対象部署にヒアリングを実施して、業務量と人数のバランスを見直しましょう。派遣社員の活用や外部委託を検討するのも有効です。
快適な職場環境づくり
職場環境を整えると、従業員の健康を守りつつ、集中力やモチベーションを大きく向上させる効果があります。以下の施策をぜひ検討してみてください。
- 適切な温度や湿度の管理
- 空気清浄機の導入
- 集中ブースの設置
- デジタルサイネージを活用した情報提供
- リフレッシュルームやドリンクコーナーの設置
職場環境をより効果的に改善するためには、社内アンケートを定期的に実施するのがおすすめです。
アンケートで得た意見をオフィスに反映すると、従業員の満足度を高められるだけでなく、職場への信頼感や一体感を構築できます。そのため、組織全体の生産性向上にもつながるでしょう。
社内・社外相談窓口の整備
従業員の問題を早期に解決するため、社内と社外それぞれに相談窓口を設置します。人事制度や職場環境、キャリアプランなどの相談に対応できるよう、社内窓口には人事部門から担当者を配置するのが一般的です。
一方で、社内担当者に相談しづらい問題や専門的な内容に対応するため、社外窓口も併用します。社内窓口と社外窓口の役割は以下のとおりです。
人事部門の担当者:
社内の状況を熟知している人事担当者が、適切なアドバイスを行います。
産業医や保健師:
健康やメンタルヘルスに関する相談は、専門知識のある産業医や保健師に依頼すると、適切なアドバイスが得られます。
カウンセラーなどの専門機関:
社内担当者に相談しづらい場合は、社外窓口を利用するとデリケートな問題でも話しやすいメリットがあります。
社内外窓口を設置する際は、匿名でも相談できる環境も用意するとよいでしょう。
社内担当者の育成とスキルアップ
社内に相談窓口を設置する際は、担当者の育成とスキルアップも欠かせません。担当者が従業員の多様な悩みに対応できるよう、以下の取り組みを導入しましょう。
- 外部研修の実施
専門機関による研修を通じて、カウンセリングのスキルやストレスマネジメントの知識を学びます。これによって、従業員からの相談に自信をもって対応できるようになります。 - 資格取得支援制度の導入
担当者が必要な資格を取得できるよう、費用の補助や学習時間の確保を行い、専門性を高めます。おすすめの資格は次のとおりです。
- 産業カウンセラー
- メンタルヘルス・マネジメント検定
- キャリアコンサルタント
- 衛生管理者
- 人事労務管理検定
社内担当者のスキルが高まると従業員が安心して相談できるため、問題の早期解決や企業の信頼感につながります。
健康診断の実施とフォロー
健康診断の実施は法律で義務付けられていますが、結果を活用して従業員の健康管理に役立てている企業はまだ少ないのが現状です。健康診断の目的を最大限に活かすためには、以下の施策を取り入れましょう。
- 健診データの可視化ツール導入
- 要再検査者への個別連絡と受診フォロー
- 健康指導の導入リスト
健康診断の実施とフォローは従業員の健康を支えるだけでなく、企業の持続的な成長に欠かせない重要な施策です。適切なフォローを通じて、健康的で生産性の高い職場環境を実現させましょう。
ストレスチェックの実施と結果の活用
ストレスチェックは職場全体の健康リスクを可視化するだけでなく、個々の従業員への対応や職場環境の改善に役立ちます。結果を効果的に活用するため、以下の内容を実行するとよいでしょう。
- 部署別のスコア分析
- 高ストレスの要因特定
- 具体的な改善計画の立案
- 高ストレス者への個別フォロー
ストレスチェックの結果を基にして、管理職向けの分析報告会を実施します。管理職が部下のストレス状況を把握できるため、メンタル不調の予防や早期発見につながります。また、マネジメントの方法を見直すきっかけにもなるでしょう。
社外連携がおすすめの領域
社内リソースでは難しい問い合わせに直面した場合は外部専門家と連携すると、より幅広い内容に対応できます。専門家の力を借りて、問題の早期発見や相談体制の信頼性向上を目指しましょう。外部連携がおすすめの領域は次のとおりです。
- 専門的な相談やカウンセリング
- 休職者の職場復帰支援
専門的な相談やカウンセリング
従業員から寄せられる問い合わせの中には、社内での対応が難しいケースも多くあるのではないでしょうか。その場合は外部のリソースを活用しましょう。
メンタルヘルス:
産業医や保健師、カウンセラーと連携して、従業員のメンタルヘルスのケアを行います。高ストレス者との対応や復職支援の場面で特に有効です。
法的なトラブル:
労務問題やハラスメントが発生した場合は、弁護士などに相談すると適切に対応できます。
職場環境の改善:
外部コンサルタントの知見を活用し、職場環境の課題分析や改善策の立案を進めます。
外部の専門家が介入すると、社内では見落とされがちな問題点が見つかるのもメリットです。
休職者の職場復帰支援
休職者の対応は、人事担当者にとって特に難しい業務の1つではないでしょうか。産業医や保健師と連携し、一人ひとりに合わせて丁寧にサポートするのが大切です。一般的には以下の方法で対応します。
- 休職中の定期的な連絡や産業医面談
- 復職に向けた計画策定や復職支援プログラムの提供
- 復職後の面談や受け入れ先部署のフォロー
休職者の対応を適切に行い、安心して復職できる環境を整えましょう。これにより、休職の再発防止や人材の定着に寄与します。
健康管理と相談体制構築法についてよくある質問
健康管理と相談体制構築法についてよくある質問をまとめました。ぜひ参考にしてください。
- 社内担当者に必要な資格はありますか?
- 健康診断の受診率100%を達成するコツはありますか?
- 休職者の復職支援で気をつけることはありますか?
- 相談窓口の利用率が低い場合、どのように対策をしたらよいですか?
社内担当者に必要な資格はありますか?
社内担当者の資格は必須ではありませんが、産業カウンセラーやメンタルヘルス・マネジメント検定、キャリアコンサルタントなどの資格があるとよいでしょう。従業員から信頼が得られるだけでなく、相談件数の増加や早期解決にもつながります。
研修や講習会に参加してもらい、最新の知識を習得することも大切です。また、資格取得支援制度を企業で導入すると、担当者のモチベーション向上にもつながります。
健康診断の受診率100%を達成するコツはありますか?
健康診断の受診率を100%にするためには、受診しやすい環境づくりが大切です。効果的な取り組みは以下のとおりです。
- リマインドメールの配信
- Web予約システムの導入
- 経営陣からの通達
- 未受診者へのフォロー
上記の取り組みを行なっても、業務の都合や個人的な理由などで受診率100%の達成が難しいケースも考えられます。その場合は「健康診断を受診するのは労働者の義務」であることを伝え、理解を深めてもらうことが大切です。
また、健康診断について就業規則に記載するのも有効です。「従業員が健康診断を受診しない場合は、懲戒処分の対象とする」旨を記載している企業も多くあります。
休職者の復職支援で気をつけることはありますか?
復職支援では復職者が安心して職場に適応できるよう、段階的にサポートします。主な方法は以下の3つです。
復職者一人ひとりの状況を見極めて柔軟に対応すると、再休職や離職のリスクを抑えられます。
相談窓口の利用率が低い場合、どのように対策をしたらよいですか?
相談窓口の利用率が低い場合は、社内掲示板などで定期的に周知しつつ、安心して利用できる環境を整えることが大切です。具体的な方法は次のとおりです。
- 相談窓口の定期的な周知
- 予約システムの導入
- オンライン相談の受付
- 守秘義務の徹底
「いつでも安心して相談できる」と感じられる環境を構築すると、利用率の向上につながります。
まとめ
従業員の健康管理と相談体制の整備は、人事担当者にとって欠かせない重要な役割です。従業員の心身の健康を守ると、企業の生産性向上や職場全体のエンゲージメント強化につながります。
効果的な支援を実現するためには、社内で対応できる業務と、社外の専門家と連携すべき領域を明確に分けることが重要です。それによって、柔軟かつ効率的に従業員一人ひとりをサポートできます。
人事担当者としての力を発揮しながら、社内外のリソースを最大限に活用し、健康で活気あふれる職場づくりを目指しましょう。